今月へ
[カールしている人

 3月28日
電車に乗っていると、前の座席の人が突然髪をカールさせはじめた。目の前の手の
動きがあまりにきれいなので、思わずカメラを取り出し撮っていた。
3年ぶりに友達の宏子さんに会いに行った。ゆっくり話すのは15年ぶりくらいになる。
宏子さんは子供を育てている間は自由にする時間も気持ちの余裕ももてない、という話
をしてくれて、学生時代に一緒に旅行したころを懐かしんだ。同級生の友達のこととか
も少し話したが、キャンバスでのことは互いにほとんど記憶にない、というのがおかし
かった。それぞれいろいろあったことを報告しあっていると、気持ちが落ち着いてくる。
おかれている状況が違っていることも、離れていることも自然に受け止め会えていたと
思う。かえって時間が経った今だから打ち溶け合えたということもあるのかな、と思う。
それぞれ自分の決めた道を歩いてきている今だから。道といえば、私が駅につくと宏子
さんが車で迎えにきてくれてずっと運転していろいろ連れていってくれた。運転できない
私は、甘やかされるように助手席でぼーとしていた。ぼーとさせてくれていた。同性の
友達はありがいものだなと思った。多和田葉子の小説『ヒナギクのお茶の場合』にも同性
の友達といる似たシーンがあった。こちらはボートに二人で乗って「わたし」はハンナに
ボートを漕いでもらっている。小説の二人と同じような年齢の私たち。
[光源の数だけ影がある]
3月28日
電車に乗っていると、前の座席の人が突然髪をカールさせはじめた。目の前の手の
動きがあまりにきれいなので、思わずカメラを取り出し撮っていた。
3年ぶりに友達の宏子さんに会いに行った。ゆっくり話すのは15年ぶりくらいになる。
宏子さんは子供を育てている間は自由にする時間も気持ちの余裕ももてない、という話
をしてくれて、学生時代に一緒に旅行したころを懐かしんだ。同級生の友達のこととか
も少し話したが、キャンバスでのことは互いにほとんど記憶にない、というのがおかし
かった。それぞれいろいろあったことを報告しあっていると、気持ちが落ち着いてくる。
おかれている状況が違っていることも、離れていることも自然に受け止め会えていたと
思う。かえって時間が経った今だから打ち溶け合えたということもあるのかな、と思う。
それぞれ自分の決めた道を歩いてきている今だから。道といえば、私が駅につくと宏子
さんが車で迎えにきてくれてずっと運転していろいろ連れていってくれた。運転できない
私は、甘やかされるように助手席でぼーとしていた。ぼーとさせてくれていた。同性の
友達はありがいものだなと思った。多和田葉子の小説『ヒナギクのお茶の場合』にも同性
の友達といる似たシーンがあった。こちらはボートに二人で乗って「わたし」はハンナに
ボートを漕いでもらっている。小説の二人と同じような年齢の私たち。
[光源の数だけ影がある]
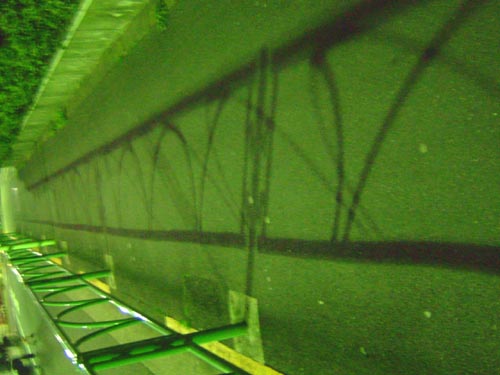 3月27日
夜歩いていると足元に複雑なアーチがかかっていた。ガードレールのアーチはすっきり一つ
なのに。昼には一つの黒いアーチを地面にみなれていた目が異変を感じ、すこし驚き、あちこち
に立っている照明に気付く。光源の数だけ影がある。そう納得したけれど、それでも、複雑な
アーチをおもしろいなぁと思う感覚は消えない。
花粉がすごいので、鼻の薬を飲んでいてもむずむずする。バラ甜茶というのを買って飲んで
みている。買ったから飲むけれど、すごい味。慣れないと漢方薬みたいに薬っぽい。去年は、
ガヴァ茶を飲んでいた。耳のなかもかゆい。
きょう本を読んでいて心に残ったことば
「行うごとくに人はなり、望むごとくに運命は形づくられる」 アーラヤヌカ・ウパニシャッド
自分の行為を通じて、いろいろ自分で決めながら、人は成ってゆく、ということだろうか。
厳しい言葉だけれど、何かしようとするとき、希望をもたせてくれる言葉だと思った。
[さがしだす]
3月27日
夜歩いていると足元に複雑なアーチがかかっていた。ガードレールのアーチはすっきり一つ
なのに。昼には一つの黒いアーチを地面にみなれていた目が異変を感じ、すこし驚き、あちこち
に立っている照明に気付く。光源の数だけ影がある。そう納得したけれど、それでも、複雑な
アーチをおもしろいなぁと思う感覚は消えない。
花粉がすごいので、鼻の薬を飲んでいてもむずむずする。バラ甜茶というのを買って飲んで
みている。買ったから飲むけれど、すごい味。慣れないと漢方薬みたいに薬っぽい。去年は、
ガヴァ茶を飲んでいた。耳のなかもかゆい。
きょう本を読んでいて心に残ったことば
「行うごとくに人はなり、望むごとくに運命は形づくられる」 アーラヤヌカ・ウパニシャッド
自分の行為を通じて、いろいろ自分で決めながら、人は成ってゆく、ということだろうか。
厳しい言葉だけれど、何かしようとするとき、希望をもたせてくれる言葉だと思った。
[さがしだす]
 3月22日
さがしだす
人混みのなかで、なんとなく目をあげると、二つの眼がこちらを向いていて、気付くと、
探していたわけでもないのに、会いたかった人がいた、という不思議なことが何度かあった。
その頃制服の深緑色のブレザーを着ていて、制服の中の体の中の砂の下にうもれていて、
ワタシは出てきていなかった意識だった。だからその不思議なことについて、
嬉しい気持ちに覆われてしまい、思いめぐらせたりできなかった。
不思議なことはどうして起こったのだろう。
出てきていない意識だったワタシのことを思いめぐらすと、
体の中で砂に埋もれていて光を見られなかったと思う。
遠く体の皮膚や瞳が感じた光を、埋もれた砂の下で乾いたスポンジのように吸い取って、
そのなかにごくわずかに交じっている会いたい人の情報を
むさぼるように探し出していたのかもしれない。
会いたい人はきっと明るい花のような光だったろう。
花屋さんが切り花の茎を差して止め花籠をつくるときに使う乾いたスポンジのような
深緑色の塊のことを、オアシスと呼んでいるのを聞いたとき、
乾いていることはみじめなことではなくて
熱帯の光に降りそそがれながらすらりとした椰子の木影で、
きらきら光る波を見ているようにすてきに思えてわくわくした。
触らせてもらったオアシスは、手に載せると意外なほど軽くて
でも深緑の塊を握ると、ふかっとした手触りなのにとてもしっかりしている。
そして水をいくらでも吸収する。だから、花にとってはオアシスというわけなのか。
ワタシはまるで地の中の発芽していない種のように、
闇の中、砂の下に埋もれていて体のどこともわからないところで、
降りてくる微かな光を飽くことなく吸い込んでいたらしい。
深緑の塊がいくらでも水を吸い込むように、赤い花の茎が差されるのを待っているように。
これっという光が降りてくるのを
忘れていても
気付いてなくても
さがしていた
そして なんとなく目をあげる
(3/24)
[食べる日日]
3月22日
さがしだす
人混みのなかで、なんとなく目をあげると、二つの眼がこちらを向いていて、気付くと、
探していたわけでもないのに、会いたかった人がいた、という不思議なことが何度かあった。
その頃制服の深緑色のブレザーを着ていて、制服の中の体の中の砂の下にうもれていて、
ワタシは出てきていなかった意識だった。だからその不思議なことについて、
嬉しい気持ちに覆われてしまい、思いめぐらせたりできなかった。
不思議なことはどうして起こったのだろう。
出てきていない意識だったワタシのことを思いめぐらすと、
体の中で砂に埋もれていて光を見られなかったと思う。
遠く体の皮膚や瞳が感じた光を、埋もれた砂の下で乾いたスポンジのように吸い取って、
そのなかにごくわずかに交じっている会いたい人の情報を
むさぼるように探し出していたのかもしれない。
会いたい人はきっと明るい花のような光だったろう。
花屋さんが切り花の茎を差して止め花籠をつくるときに使う乾いたスポンジのような
深緑色の塊のことを、オアシスと呼んでいるのを聞いたとき、
乾いていることはみじめなことではなくて
熱帯の光に降りそそがれながらすらりとした椰子の木影で、
きらきら光る波を見ているようにすてきに思えてわくわくした。
触らせてもらったオアシスは、手に載せると意外なほど軽くて
でも深緑の塊を握ると、ふかっとした手触りなのにとてもしっかりしている。
そして水をいくらでも吸収する。だから、花にとってはオアシスというわけなのか。
ワタシはまるで地の中の発芽していない種のように、
闇の中、砂の下に埋もれていて体のどこともわからないところで、
降りてくる微かな光を飽くことなく吸い込んでいたらしい。
深緑の塊がいくらでも水を吸い込むように、赤い花の茎が差されるのを待っているように。
これっという光が降りてくるのを
忘れていても
気付いてなくても
さがしていた
そして なんとなく目をあげる
(3/24)
[食べる日日]




 3月21日
花粉が怖くてマスクをして写真なんか撮っているけれど、花粉花粉花粉花粉と
他の物は何も眼に入らないかのように夢中で足に花粉団子を作って付けている蜂
がいて、ふと気が引けた。気が引けたのは花粉のことではなくて、蜂はきっと訳の
わからないものを近づける人間のことを知っていながら、危険よりも花粉団子を
生きのびるために優先している、と思ったからだ。蜂のしていることのシンプル
さに照らされて、過剰すぎるこちらは、どうしたら引け目を感じずに過剰すぎる
ことを引き受けられるのかなと、立ち止まってしまう。長くて100年の人の生涯は
長いのか短いのか。過剰といっても無駄なことばかりで頭も体もうまく使えてな
んかいない。今日夫の先祖の墓参りをしながら線香をあげていると、どんどん燃
えてしまって短くなっていく線香と、流れていってしまうこの時間は何なのだろ
うと思ってしまった。知らない人の入っている墓の前で手を合わせても、じつは
何だかよく分からない、家の人が喜んでいるからいいことをしているような気が
するけれど、という程の自分を支えているのは、食べることについて言えば野菜
を作ることでも、料理をして食事の準備をすることでもない。蜂にフンッと言わ
れそうな、花の中に蜂が食べ物を集めるために働いているのを見つけて撮り、そ
んなことがあったと言葉で書いて置いたりすることなのだ。そしてこんなことの
繰り返しからあるとき詩を書けるきっかけをつかんで、詩を書くこと。書いて、
発表して、外と繋がること。読んでもらうこと。で、それからなんだといえば、
まったくおこがましいかもしれないのだけれど、読んでくれた人にとっていくらか
でも読んだことでパワーになるようでありたいということなのだ。また蜂がフンッ
と言うかもしれないけれど。
[いまへ近い順序の光景]
3月21日
花粉が怖くてマスクをして写真なんか撮っているけれど、花粉花粉花粉花粉と
他の物は何も眼に入らないかのように夢中で足に花粉団子を作って付けている蜂
がいて、ふと気が引けた。気が引けたのは花粉のことではなくて、蜂はきっと訳の
わからないものを近づける人間のことを知っていながら、危険よりも花粉団子を
生きのびるために優先している、と思ったからだ。蜂のしていることのシンプル
さに照らされて、過剰すぎるこちらは、どうしたら引け目を感じずに過剰すぎる
ことを引き受けられるのかなと、立ち止まってしまう。長くて100年の人の生涯は
長いのか短いのか。過剰といっても無駄なことばかりで頭も体もうまく使えてな
んかいない。今日夫の先祖の墓参りをしながら線香をあげていると、どんどん燃
えてしまって短くなっていく線香と、流れていってしまうこの時間は何なのだろ
うと思ってしまった。知らない人の入っている墓の前で手を合わせても、じつは
何だかよく分からない、家の人が喜んでいるからいいことをしているような気が
するけれど、という程の自分を支えているのは、食べることについて言えば野菜
を作ることでも、料理をして食事の準備をすることでもない。蜂にフンッと言わ
れそうな、花の中に蜂が食べ物を集めるために働いているのを見つけて撮り、そ
んなことがあったと言葉で書いて置いたりすることなのだ。そしてこんなことの
繰り返しからあるとき詩を書けるきっかけをつかんで、詩を書くこと。書いて、
発表して、外と繋がること。読んでもらうこと。で、それからなんだといえば、
まったくおこがましいかもしれないのだけれど、読んでくれた人にとっていくらか
でも読んだことでパワーになるようでありたいということなのだ。また蜂がフンッ
と言うかもしれないけれど。
[いまへ近い順序の光景]


 3月19日
いまここに言葉を置いて一日を終えようとするとき、夕方から昼それから朝へと
記憶を遡ったりしない。一日をすばやく飛び移って朝起きてからのことを思い出し
はじめるのはどうしてだろう。近い時間から遠い時間へと波のように伝ってゆくの
は苦手なようにできているのかも知れない。
りっとさん、とは樋口えみこさんを通して知り合ったのだが、りっとさんが第一詩集
『空にからだの船、青く』を草原詩社から里都潤弥の名前で出版した。樋口さんプロデ
ュースの、もういちど生まれるためにシリーズ、一号。おめでとうございます、りっと
さん、樋口さん。
この詩集のなかでとても凄い詩に私は巡りあった。タイトルは「視力」。こんなに難
しいものが詩にできるのだろうか、とふと多和田葉子さんの小説「旅をする裸の眼」の
言葉(視力とは裂け目なのでまさにそこが見えない)を思いだした。りっとさんは、その
見えないところを感じながら、見るという視力の意味からジャンプして自分の世界を詩
で開いてゆく。いい感じだなぁと思う。
視力 里都潤弥
瞳の中に海が産まれる
内蔵の船が泳いでいる
いつまでも夢のようなスピード
僕らが住む国を探している
その速さが視力
瞳の底から産まれる
高さ2mの山たち
かかとの中の気持ちが
地面を支えていて
僕らのさみしくない国が見える
そこにある歌が君の数を数えて
その大きさが視力
瞳の表面は乾いて
きれいに剥がれている
せめて砂に埋めたら
君と寂しさが生えてきた
内臓の船は食べられ
2mの山は踏み固められても
収穫の祈りをささげて
寂しさだけを刈り取ることが出来る
瞳の表面は乾いて
寂しくない国なんていらない
刈り残された君が
揺れながら風を産んで
僕の身体に刺さっている
その強さが視力
ここに書き写させていただきながら、はっきりとイメージが体感されてきた。
刈り取られる寂しさという丈の高い草や、その後にのこったのは、刈り取るときに
踏み固めてしまった君の気持ちと、そこここで細い茎の君といういろいろな草たち
が揺れながら風を産んでいる情景。そして草たちは鋭く僕の身体に刺さっている。
寂しさを粗末にした僕へ「寂しくない国なんていらない」と刺さるつよさが視力だ
というのだから、なんて激しい向き合い方をしているのだろう。書いた言葉がねじれ
ながら、濃く香る。言葉が熱を持っている。その熱に魅せられる。
[金沢21世紀美術館]
3月19日
いまここに言葉を置いて一日を終えようとするとき、夕方から昼それから朝へと
記憶を遡ったりしない。一日をすばやく飛び移って朝起きてからのことを思い出し
はじめるのはどうしてだろう。近い時間から遠い時間へと波のように伝ってゆくの
は苦手なようにできているのかも知れない。
りっとさん、とは樋口えみこさんを通して知り合ったのだが、りっとさんが第一詩集
『空にからだの船、青く』を草原詩社から里都潤弥の名前で出版した。樋口さんプロデ
ュースの、もういちど生まれるためにシリーズ、一号。おめでとうございます、りっと
さん、樋口さん。
この詩集のなかでとても凄い詩に私は巡りあった。タイトルは「視力」。こんなに難
しいものが詩にできるのだろうか、とふと多和田葉子さんの小説「旅をする裸の眼」の
言葉(視力とは裂け目なのでまさにそこが見えない)を思いだした。りっとさんは、その
見えないところを感じながら、見るという視力の意味からジャンプして自分の世界を詩
で開いてゆく。いい感じだなぁと思う。
視力 里都潤弥
瞳の中に海が産まれる
内蔵の船が泳いでいる
いつまでも夢のようなスピード
僕らが住む国を探している
その速さが視力
瞳の底から産まれる
高さ2mの山たち
かかとの中の気持ちが
地面を支えていて
僕らのさみしくない国が見える
そこにある歌が君の数を数えて
その大きさが視力
瞳の表面は乾いて
きれいに剥がれている
せめて砂に埋めたら
君と寂しさが生えてきた
内臓の船は食べられ
2mの山は踏み固められても
収穫の祈りをささげて
寂しさだけを刈り取ることが出来る
瞳の表面は乾いて
寂しくない国なんていらない
刈り残された君が
揺れながら風を産んで
僕の身体に刺さっている
その強さが視力
ここに書き写させていただきながら、はっきりとイメージが体感されてきた。
刈り取られる寂しさという丈の高い草や、その後にのこったのは、刈り取るときに
踏み固めてしまった君の気持ちと、そこここで細い茎の君といういろいろな草たち
が揺れながら風を産んでいる情景。そして草たちは鋭く僕の身体に刺さっている。
寂しさを粗末にした僕へ「寂しくない国なんていらない」と刺さるつよさが視力だ
というのだから、なんて激しい向き合い方をしているのだろう。書いた言葉がねじれ
ながら、濃く香る。言葉が熱を持っている。その熱に魅せられる。
[金沢21世紀美術館]

 3月13日
「共鳴、ここ・から」を見にいってきた。
21世紀を共に生き延びるための意識、共存、集合知への移行を説く長谷川祐子さん
の造った「エゴフーガル」という言葉と共に、見て回る。
個の境界を維持しつつ、意識の磁場を共有する「積極的な遠心力をもって他者や世界
とつながっていく、新たな主体のあり方」。そんな共鳴や振動を感じる作品たちだった
けれど、もっとも伝わってきたのは細い無数ロープでさまざまな日常の物を組み入れた
巨大なシャンデリアのようなサラ・ジーの作品だった。吹き抜けの階段のガラスのエレ
ベーターのところにあった。大きなコラージュなのに静かにかすかに揺れている。よく
みると地階に置かれた扇風機が首を振って回っていて、扇風機に結んだ紐が扇風機が首
をふるのにつれて大きなオブジェ全体を揺らしているのだった。
不安定な揺らぎや結ばれ方は、脳のシナプスの網目状に枝や蔓や細いワイヤーなどで様々
なものを結びつけた「ブレイン・フォレスト」にも感じられた。高い天井の広い空間いっぱいに
様々な物を結びつけ吊られた枝をみていると全てのことを忘れて見入ってしまった。ごくちいさ
な黄色や白や紫の花、赤い実、柄のとれた傘、花と葉で造った鳥、ペットボトルを切った
リボン、小さな恐竜、流木のような発泡スチロールのかけら、しおれた木の実や、よく見る
と本物の鳥の巣や蝉の抜け殻なども結びつけられている。スピーカーやイカ吊り船のランプ
もある。銀杏の黄色い葉、紅葉の赤い葉、枯れた笹の葉なども結んであり、きれいで見飽
きない。それらをソファーに仰向けに寝て見上げることもできた。様々な生活シーンや様々
な風景が、見つめていると見えてきた。春も秋も夏も冬も。脳の記憶はいまここにある展示
のようにいまあるのだということが感じられてくる。断片が細い繋がりで。
人々の脳が、枝に花や日常の物が結ばれて縦横に細く網の目になっているように、
人と人との関係も記憶として網目に結ばれている、危うく、けれどいまここに記憶として
灯りながらあり、別々に記憶が響きあっておおきな記憶を繋いでいると意識させられた。
私の脳の森もそんなふうに振動してきた。
別の部屋ではビー玉だけを広い床に並べて造った世界地図の作品は、ビー玉の危うさが、
ちょっと誰かが指で押したりしたら、世界が崩れてしまうというイメージを震わせた。
一緒にSさんとSさんの子供の小学3年生のともちゃんと見て回ったのだけれど美術館がガラス
の壁で円状にすべて覆われていたので外がみえてとても気分が楽だった。ともちゃんもプール
の底に入ったり、真ん中に池のある卓球台で遊んだり楽しそうだったのでよかった。
[それでも笑顔で]
3月13日
「共鳴、ここ・から」を見にいってきた。
21世紀を共に生き延びるための意識、共存、集合知への移行を説く長谷川祐子さん
の造った「エゴフーガル」という言葉と共に、見て回る。
個の境界を維持しつつ、意識の磁場を共有する「積極的な遠心力をもって他者や世界
とつながっていく、新たな主体のあり方」。そんな共鳴や振動を感じる作品たちだった
けれど、もっとも伝わってきたのは細い無数ロープでさまざまな日常の物を組み入れた
巨大なシャンデリアのようなサラ・ジーの作品だった。吹き抜けの階段のガラスのエレ
ベーターのところにあった。大きなコラージュなのに静かにかすかに揺れている。よく
みると地階に置かれた扇風機が首を振って回っていて、扇風機に結んだ紐が扇風機が首
をふるのにつれて大きなオブジェ全体を揺らしているのだった。
不安定な揺らぎや結ばれ方は、脳のシナプスの網目状に枝や蔓や細いワイヤーなどで様々
なものを結びつけた「ブレイン・フォレスト」にも感じられた。高い天井の広い空間いっぱいに
様々な物を結びつけ吊られた枝をみていると全てのことを忘れて見入ってしまった。ごくちいさ
な黄色や白や紫の花、赤い実、柄のとれた傘、花と葉で造った鳥、ペットボトルを切った
リボン、小さな恐竜、流木のような発泡スチロールのかけら、しおれた木の実や、よく見る
と本物の鳥の巣や蝉の抜け殻なども結びつけられている。スピーカーやイカ吊り船のランプ
もある。銀杏の黄色い葉、紅葉の赤い葉、枯れた笹の葉なども結んであり、きれいで見飽
きない。それらをソファーに仰向けに寝て見上げることもできた。様々な生活シーンや様々
な風景が、見つめていると見えてきた。春も秋も夏も冬も。脳の記憶はいまここにある展示
のようにいまあるのだということが感じられてくる。断片が細い繋がりで。
人々の脳が、枝に花や日常の物が結ばれて縦横に細く網の目になっているように、
人と人との関係も記憶として網目に結ばれている、危うく、けれどいまここに記憶として
灯りながらあり、別々に記憶が響きあっておおきな記憶を繋いでいると意識させられた。
私の脳の森もそんなふうに振動してきた。
別の部屋ではビー玉だけを広い床に並べて造った世界地図の作品は、ビー玉の危うさが、
ちょっと誰かが指で押したりしたら、世界が崩れてしまうというイメージを震わせた。
一緒にSさんとSさんの子供の小学3年生のともちゃんと見て回ったのだけれど美術館がガラス
の壁で円状にすべて覆われていたので外がみえてとても気分が楽だった。ともちゃんもプール
の底に入ったり、真ん中に池のある卓球台で遊んだり楽しそうだったのでよかった。
[それでも笑顔で]
 3月9日
心配なこと、あまり良くない方へ気がかりなとき、はてしなくネットサーフィンを
している自分に気付く。次ぎから次ぎへと興味を追ってゆきながら、やめられなくなって
しまう。心配事を忘れられるからという理由など頭にない。ただただ取り憑かれたように
やめられなくなって、目がきしんで、痛くなりだし、疲れて胸がつかえてくると、ようやく
吐きそうなほど気持ち悪くなって止める。言葉にしてみると、なんだか過食症や買い物が
止まらない症候群の感じと似ていると思った。ただ物ではなく情報を読む、ということ
に置き換わっただけ。心配から逃げているという意識ではなく、次ぎから次ぎへ細部
が枝分かれして、見たい読みたいものがどんどん移って移動してゆく。だから追いかける。
止められなくなる。酔ったようになっているのかも知れない。酔っているのだとしたら
飲酒に近いのだろうか。そんな日は睡眠時間もなくなるので次ぎの日は体が辛くなる。頭が
まわらないから考え込めない。それでカタルシスになっているかといえばそうでもない。
奇妙な混乱に落ちて不信感や落胆や苦しさが体を覆っているとき、ふと多和田葉子の
『ヒナギクのお茶の場合』を読んだ。すると混乱したところへ真っ直ぐに言葉のエネルギー
が注がれて、絡まったものがするすると解け脳がすっきりした。やっぱり多和田葉子の
言葉はいい。
川上亜紀さんの詩集『酸素スル、春』七月堂刊を読む。私の詩誌『エメット』に書いてくれた
「凹む夏」も入っている。螺旋階段がループしているようにうまく運ばない現実から、夢の
現実へ上っていってはまた降りてくる世界は独特な世界だ。夜眠れないのでベッドをずらして
スプーンで土を削りとってゆき、そのベッドの下が土だというのも変だが、私だけの墓穴が欲し
かったので掘るという理由も可笑しい。そして「その穴は「新明解」という名前になった」
という。この奇妙さは書くことで困難を超えてゆくときに起こるユーモア。川上さんの詩の言葉
は夢をくぐりながら手に負えない生を言葉を書く手とともに本人が一緒に伴走してゆくときに獲得
したユーモアなのだった。読みながら漬かりもせず溺れもせず私も共に伴走しながら、顔をゆがめた
りくすっと笑っていたりした。
[マスクをしたまま深呼吸]
3月9日
心配なこと、あまり良くない方へ気がかりなとき、はてしなくネットサーフィンを
している自分に気付く。次ぎから次ぎへと興味を追ってゆきながら、やめられなくなって
しまう。心配事を忘れられるからという理由など頭にない。ただただ取り憑かれたように
やめられなくなって、目がきしんで、痛くなりだし、疲れて胸がつかえてくると、ようやく
吐きそうなほど気持ち悪くなって止める。言葉にしてみると、なんだか過食症や買い物が
止まらない症候群の感じと似ていると思った。ただ物ではなく情報を読む、ということ
に置き換わっただけ。心配から逃げているという意識ではなく、次ぎから次ぎへ細部
が枝分かれして、見たい読みたいものがどんどん移って移動してゆく。だから追いかける。
止められなくなる。酔ったようになっているのかも知れない。酔っているのだとしたら
飲酒に近いのだろうか。そんな日は睡眠時間もなくなるので次ぎの日は体が辛くなる。頭が
まわらないから考え込めない。それでカタルシスになっているかといえばそうでもない。
奇妙な混乱に落ちて不信感や落胆や苦しさが体を覆っているとき、ふと多和田葉子の
『ヒナギクのお茶の場合』を読んだ。すると混乱したところへ真っ直ぐに言葉のエネルギー
が注がれて、絡まったものがするすると解け脳がすっきりした。やっぱり多和田葉子の
言葉はいい。
川上亜紀さんの詩集『酸素スル、春』七月堂刊を読む。私の詩誌『エメット』に書いてくれた
「凹む夏」も入っている。螺旋階段がループしているようにうまく運ばない現実から、夢の
現実へ上っていってはまた降りてくる世界は独特な世界だ。夜眠れないのでベッドをずらして
スプーンで土を削りとってゆき、そのベッドの下が土だというのも変だが、私だけの墓穴が欲し
かったので掘るという理由も可笑しい。そして「その穴は「新明解」という名前になった」
という。この奇妙さは書くことで困難を超えてゆくときに起こるユーモア。川上さんの詩の言葉
は夢をくぐりながら手に負えない生を言葉を書く手とともに本人が一緒に伴走してゆくときに獲得
したユーモアなのだった。読みながら漬かりもせず溺れもせず私も共に伴走しながら、顔をゆがめた
りくすっと笑っていたりした。
[マスクをしたまま深呼吸]

 3月7日
土曜日に佐藤淳一さんの写真展『瞼と森』にいってきた。毎年同じギャラリー
なので今年の写真に重なって去年の写真が見えた。そのむこうに一昨年の「air」の
時の写真も見えた。同じギャラリーで続けるのはこんなふうになるのかと驚いた。
もちろん覚えているものだけしか見えないけれど。今年は植物、動物、魚など生きて
いるものが目についた。そしていつも思うけれど立体感を現す線がいきていた。佐藤
さんは脊髄のバランス感覚とおっしゃっていたけれど、人のカメラを捧げる腕も、
向日葵の茂りうねっている茎も構造物のように立体的に感じる。そして水と草の緑と
花の黄色が生き物感を伝えてきた。
永代橋から墨田川を撮る。ギャラリーの直ぐ下が墨田川なので写真展と川は私の中
でセットになってしまた。花粉避けマスクをしながら、るんるん歩いた。
[瞬間のピンク]
3月7日
土曜日に佐藤淳一さんの写真展『瞼と森』にいってきた。毎年同じギャラリー
なので今年の写真に重なって去年の写真が見えた。そのむこうに一昨年の「air」の
時の写真も見えた。同じギャラリーで続けるのはこんなふうになるのかと驚いた。
もちろん覚えているものだけしか見えないけれど。今年は植物、動物、魚など生きて
いるものが目についた。そしていつも思うけれど立体感を現す線がいきていた。佐藤
さんは脊髄のバランス感覚とおっしゃっていたけれど、人のカメラを捧げる腕も、
向日葵の茂りうねっている茎も構造物のように立体的に感じる。そして水と草の緑と
花の黄色が生き物感を伝えてきた。
永代橋から墨田川を撮る。ギャラリーの直ぐ下が墨田川なので写真展と川は私の中
でセットになってしまた。花粉避けマスクをしながら、るんるん歩いた。
[瞬間のピンク]
 3月2日
元木みゆきの写真展学籍番号011145が銀座のガーディアン・ガーデンでひらかれている。
すごくよい。あの中にたっていると活性化される。
そして
元木みゆきの web版 学籍番号011145もはじまっている。
切り立った信頼関係。そう言いたくなる写真はどんなときにも神経を張りつめて、撮り
ながら人のなかに立っていた彼女のぎりぎりまで気をはりつめた鋭さ、真摯さ、に支え
られている。それだからこそ突き抜けた今をからっと見せてくれる。見たことのない写真
群のこの明るさはホンモノもニセモノもない。こんなふうになまなましく、解け合えず、
信頼しあい、あからさまに、隣り合って生きている身体を目撃したことが、いえ意識化
したことがあっただろうか。自分自身に問わずにはいられない。髪と首。空のなかの×。
赤いジャージの躍動。便器のそばの動き。笑う唇と歯。作業する体。教室の乾いた群れ。
直感と努力を総動員しなくてはこれらはなかった。荒々しく、しなやかに、なにものにも
とらわれていない。共感も苦しさも悲鳴も青空にばらまくようにして、周りの友達といっしょに
打ち上げ花火にしてしまった。生命感の花火大会。リアルタイムに見なくちゃ損。こんな
にがんばって見せてくれているのだから。
3月2日
元木みゆきの写真展学籍番号011145が銀座のガーディアン・ガーデンでひらかれている。
すごくよい。あの中にたっていると活性化される。
そして
元木みゆきの web版 学籍番号011145もはじまっている。
切り立った信頼関係。そう言いたくなる写真はどんなときにも神経を張りつめて、撮り
ながら人のなかに立っていた彼女のぎりぎりまで気をはりつめた鋭さ、真摯さ、に支え
られている。それだからこそ突き抜けた今をからっと見せてくれる。見たことのない写真
群のこの明るさはホンモノもニセモノもない。こんなふうになまなましく、解け合えず、
信頼しあい、あからさまに、隣り合って生きている身体を目撃したことが、いえ意識化
したことがあっただろうか。自分自身に問わずにはいられない。髪と首。空のなかの×。
赤いジャージの躍動。便器のそばの動き。笑う唇と歯。作業する体。教室の乾いた群れ。
直感と努力を総動員しなくてはこれらはなかった。荒々しく、しなやかに、なにものにも
とらわれていない。共感も苦しさも悲鳴も青空にばらまくようにして、周りの友達といっしょに
打ち上げ花火にしてしまった。生命感の花火大会。リアルタイムに見なくちゃ損。こんな
にがんばって見せてくれているのだから。

 3月28日
電車に乗っていると、前の座席の人が突然髪をカールさせはじめた。目の前の手の
動きがあまりにきれいなので、思わずカメラを取り出し撮っていた。
3年ぶりに友達の宏子さんに会いに行った。ゆっくり話すのは15年ぶりくらいになる。
宏子さんは子供を育てている間は自由にする時間も気持ちの余裕ももてない、という話
をしてくれて、学生時代に一緒に旅行したころを懐かしんだ。同級生の友達のこととか
も少し話したが、キャンバスでのことは互いにほとんど記憶にない、というのがおかし
かった。それぞれいろいろあったことを報告しあっていると、気持ちが落ち着いてくる。
おかれている状況が違っていることも、離れていることも自然に受け止め会えていたと
思う。かえって時間が経った今だから打ち溶け合えたということもあるのかな、と思う。
それぞれ自分の決めた道を歩いてきている今だから。道といえば、私が駅につくと宏子
さんが車で迎えにきてくれてずっと運転していろいろ連れていってくれた。運転できない
私は、甘やかされるように助手席でぼーとしていた。ぼーとさせてくれていた。同性の
友達はありがいものだなと思った。多和田葉子の小説『ヒナギクのお茶の場合』にも同性
の友達といる似たシーンがあった。こちらはボートに二人で乗って「わたし」はハンナに
ボートを漕いでもらっている。小説の二人と同じような年齢の私たち。
[光源の数だけ影がある]
3月28日
電車に乗っていると、前の座席の人が突然髪をカールさせはじめた。目の前の手の
動きがあまりにきれいなので、思わずカメラを取り出し撮っていた。
3年ぶりに友達の宏子さんに会いに行った。ゆっくり話すのは15年ぶりくらいになる。
宏子さんは子供を育てている間は自由にする時間も気持ちの余裕ももてない、という話
をしてくれて、学生時代に一緒に旅行したころを懐かしんだ。同級生の友達のこととか
も少し話したが、キャンバスでのことは互いにほとんど記憶にない、というのがおかし
かった。それぞれいろいろあったことを報告しあっていると、気持ちが落ち着いてくる。
おかれている状況が違っていることも、離れていることも自然に受け止め会えていたと
思う。かえって時間が経った今だから打ち溶け合えたということもあるのかな、と思う。
それぞれ自分の決めた道を歩いてきている今だから。道といえば、私が駅につくと宏子
さんが車で迎えにきてくれてずっと運転していろいろ連れていってくれた。運転できない
私は、甘やかされるように助手席でぼーとしていた。ぼーとさせてくれていた。同性の
友達はありがいものだなと思った。多和田葉子の小説『ヒナギクのお茶の場合』にも同性
の友達といる似たシーンがあった。こちらはボートに二人で乗って「わたし」はハンナに
ボートを漕いでもらっている。小説の二人と同じような年齢の私たち。
[光源の数だけ影がある]
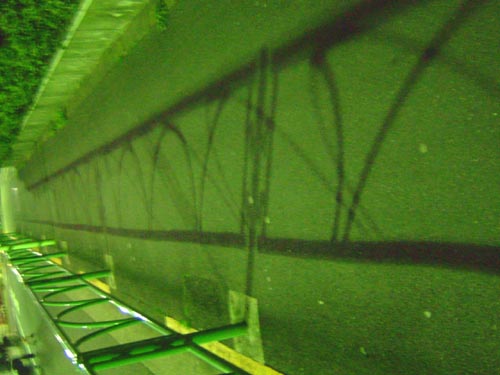 3月27日
夜歩いていると足元に複雑なアーチがかかっていた。ガードレールのアーチはすっきり一つ
なのに。昼には一つの黒いアーチを地面にみなれていた目が異変を感じ、すこし驚き、あちこち
に立っている照明に気付く。光源の数だけ影がある。そう納得したけれど、それでも、複雑な
アーチをおもしろいなぁと思う感覚は消えない。
花粉がすごいので、鼻の薬を飲んでいてもむずむずする。バラ甜茶というのを買って飲んで
みている。買ったから飲むけれど、すごい味。慣れないと漢方薬みたいに薬っぽい。去年は、
ガヴァ茶を飲んでいた。耳のなかもかゆい。
きょう本を読んでいて心に残ったことば
「行うごとくに人はなり、望むごとくに運命は形づくられる」 アーラヤヌカ・ウパニシャッド
自分の行為を通じて、いろいろ自分で決めながら、人は成ってゆく、ということだろうか。
厳しい言葉だけれど、何かしようとするとき、希望をもたせてくれる言葉だと思った。
[さがしだす]
3月27日
夜歩いていると足元に複雑なアーチがかかっていた。ガードレールのアーチはすっきり一つ
なのに。昼には一つの黒いアーチを地面にみなれていた目が異変を感じ、すこし驚き、あちこち
に立っている照明に気付く。光源の数だけ影がある。そう納得したけれど、それでも、複雑な
アーチをおもしろいなぁと思う感覚は消えない。
花粉がすごいので、鼻の薬を飲んでいてもむずむずする。バラ甜茶というのを買って飲んで
みている。買ったから飲むけれど、すごい味。慣れないと漢方薬みたいに薬っぽい。去年は、
ガヴァ茶を飲んでいた。耳のなかもかゆい。
きょう本を読んでいて心に残ったことば
「行うごとくに人はなり、望むごとくに運命は形づくられる」 アーラヤヌカ・ウパニシャッド
自分の行為を通じて、いろいろ自分で決めながら、人は成ってゆく、ということだろうか。
厳しい言葉だけれど、何かしようとするとき、希望をもたせてくれる言葉だと思った。
[さがしだす]
 3月22日
さがしだす
人混みのなかで、なんとなく目をあげると、二つの眼がこちらを向いていて、気付くと、
探していたわけでもないのに、会いたかった人がいた、という不思議なことが何度かあった。
その頃制服の深緑色のブレザーを着ていて、制服の中の体の中の砂の下にうもれていて、
ワタシは出てきていなかった意識だった。だからその不思議なことについて、
嬉しい気持ちに覆われてしまい、思いめぐらせたりできなかった。
不思議なことはどうして起こったのだろう。
出てきていない意識だったワタシのことを思いめぐらすと、
体の中で砂に埋もれていて光を見られなかったと思う。
遠く体の皮膚や瞳が感じた光を、埋もれた砂の下で乾いたスポンジのように吸い取って、
そのなかにごくわずかに交じっている会いたい人の情報を
むさぼるように探し出していたのかもしれない。
会いたい人はきっと明るい花のような光だったろう。
花屋さんが切り花の茎を差して止め花籠をつくるときに使う乾いたスポンジのような
深緑色の塊のことを、オアシスと呼んでいるのを聞いたとき、
乾いていることはみじめなことではなくて
熱帯の光に降りそそがれながらすらりとした椰子の木影で、
きらきら光る波を見ているようにすてきに思えてわくわくした。
触らせてもらったオアシスは、手に載せると意外なほど軽くて
でも深緑の塊を握ると、ふかっとした手触りなのにとてもしっかりしている。
そして水をいくらでも吸収する。だから、花にとってはオアシスというわけなのか。
ワタシはまるで地の中の発芽していない種のように、
闇の中、砂の下に埋もれていて体のどこともわからないところで、
降りてくる微かな光を飽くことなく吸い込んでいたらしい。
深緑の塊がいくらでも水を吸い込むように、赤い花の茎が差されるのを待っているように。
これっという光が降りてくるのを
忘れていても
気付いてなくても
さがしていた
そして なんとなく目をあげる
(3/24)
[食べる日日]
3月22日
さがしだす
人混みのなかで、なんとなく目をあげると、二つの眼がこちらを向いていて、気付くと、
探していたわけでもないのに、会いたかった人がいた、という不思議なことが何度かあった。
その頃制服の深緑色のブレザーを着ていて、制服の中の体の中の砂の下にうもれていて、
ワタシは出てきていなかった意識だった。だからその不思議なことについて、
嬉しい気持ちに覆われてしまい、思いめぐらせたりできなかった。
不思議なことはどうして起こったのだろう。
出てきていない意識だったワタシのことを思いめぐらすと、
体の中で砂に埋もれていて光を見られなかったと思う。
遠く体の皮膚や瞳が感じた光を、埋もれた砂の下で乾いたスポンジのように吸い取って、
そのなかにごくわずかに交じっている会いたい人の情報を
むさぼるように探し出していたのかもしれない。
会いたい人はきっと明るい花のような光だったろう。
花屋さんが切り花の茎を差して止め花籠をつくるときに使う乾いたスポンジのような
深緑色の塊のことを、オアシスと呼んでいるのを聞いたとき、
乾いていることはみじめなことではなくて
熱帯の光に降りそそがれながらすらりとした椰子の木影で、
きらきら光る波を見ているようにすてきに思えてわくわくした。
触らせてもらったオアシスは、手に載せると意外なほど軽くて
でも深緑の塊を握ると、ふかっとした手触りなのにとてもしっかりしている。
そして水をいくらでも吸収する。だから、花にとってはオアシスというわけなのか。
ワタシはまるで地の中の発芽していない種のように、
闇の中、砂の下に埋もれていて体のどこともわからないところで、
降りてくる微かな光を飽くことなく吸い込んでいたらしい。
深緑の塊がいくらでも水を吸い込むように、赤い花の茎が差されるのを待っているように。
これっという光が降りてくるのを
忘れていても
気付いてなくても
さがしていた
そして なんとなく目をあげる
(3/24)
[食べる日日]




 3月21日
花粉が怖くてマスクをして写真なんか撮っているけれど、花粉花粉花粉花粉と
他の物は何も眼に入らないかのように夢中で足に花粉団子を作って付けている蜂
がいて、ふと気が引けた。気が引けたのは花粉のことではなくて、蜂はきっと訳の
わからないものを近づける人間のことを知っていながら、危険よりも花粉団子を
生きのびるために優先している、と思ったからだ。蜂のしていることのシンプル
さに照らされて、過剰すぎるこちらは、どうしたら引け目を感じずに過剰すぎる
ことを引き受けられるのかなと、立ち止まってしまう。長くて100年の人の生涯は
長いのか短いのか。過剰といっても無駄なことばかりで頭も体もうまく使えてな
んかいない。今日夫の先祖の墓参りをしながら線香をあげていると、どんどん燃
えてしまって短くなっていく線香と、流れていってしまうこの時間は何なのだろ
うと思ってしまった。知らない人の入っている墓の前で手を合わせても、じつは
何だかよく分からない、家の人が喜んでいるからいいことをしているような気が
するけれど、という程の自分を支えているのは、食べることについて言えば野菜
を作ることでも、料理をして食事の準備をすることでもない。蜂にフンッと言わ
れそうな、花の中に蜂が食べ物を集めるために働いているのを見つけて撮り、そ
んなことがあったと言葉で書いて置いたりすることなのだ。そしてこんなことの
繰り返しからあるとき詩を書けるきっかけをつかんで、詩を書くこと。書いて、
発表して、外と繋がること。読んでもらうこと。で、それからなんだといえば、
まったくおこがましいかもしれないのだけれど、読んでくれた人にとっていくらか
でも読んだことでパワーになるようでありたいということなのだ。また蜂がフンッ
と言うかもしれないけれど。
[いまへ近い順序の光景]
3月21日
花粉が怖くてマスクをして写真なんか撮っているけれど、花粉花粉花粉花粉と
他の物は何も眼に入らないかのように夢中で足に花粉団子を作って付けている蜂
がいて、ふと気が引けた。気が引けたのは花粉のことではなくて、蜂はきっと訳の
わからないものを近づける人間のことを知っていながら、危険よりも花粉団子を
生きのびるために優先している、と思ったからだ。蜂のしていることのシンプル
さに照らされて、過剰すぎるこちらは、どうしたら引け目を感じずに過剰すぎる
ことを引き受けられるのかなと、立ち止まってしまう。長くて100年の人の生涯は
長いのか短いのか。過剰といっても無駄なことばかりで頭も体もうまく使えてな
んかいない。今日夫の先祖の墓参りをしながら線香をあげていると、どんどん燃
えてしまって短くなっていく線香と、流れていってしまうこの時間は何なのだろ
うと思ってしまった。知らない人の入っている墓の前で手を合わせても、じつは
何だかよく分からない、家の人が喜んでいるからいいことをしているような気が
するけれど、という程の自分を支えているのは、食べることについて言えば野菜
を作ることでも、料理をして食事の準備をすることでもない。蜂にフンッと言わ
れそうな、花の中に蜂が食べ物を集めるために働いているのを見つけて撮り、そ
んなことがあったと言葉で書いて置いたりすることなのだ。そしてこんなことの
繰り返しからあるとき詩を書けるきっかけをつかんで、詩を書くこと。書いて、
発表して、外と繋がること。読んでもらうこと。で、それからなんだといえば、
まったくおこがましいかもしれないのだけれど、読んでくれた人にとっていくらか
でも読んだことでパワーになるようでありたいということなのだ。また蜂がフンッ
と言うかもしれないけれど。
[いまへ近い順序の光景]


 3月19日
いまここに言葉を置いて一日を終えようとするとき、夕方から昼それから朝へと
記憶を遡ったりしない。一日をすばやく飛び移って朝起きてからのことを思い出し
はじめるのはどうしてだろう。近い時間から遠い時間へと波のように伝ってゆくの
は苦手なようにできているのかも知れない。
りっとさん、とは樋口えみこさんを通して知り合ったのだが、りっとさんが第一詩集
『空にからだの船、青く』を草原詩社から里都潤弥の名前で出版した。樋口さんプロデ
ュースの、もういちど生まれるためにシリーズ、一号。おめでとうございます、りっと
さん、樋口さん。
この詩集のなかでとても凄い詩に私は巡りあった。タイトルは「視力」。こんなに難
しいものが詩にできるのだろうか、とふと多和田葉子さんの小説「旅をする裸の眼」の
言葉(視力とは裂け目なのでまさにそこが見えない)を思いだした。りっとさんは、その
見えないところを感じながら、見るという視力の意味からジャンプして自分の世界を詩
で開いてゆく。いい感じだなぁと思う。
視力 里都潤弥
瞳の中に海が産まれる
内蔵の船が泳いでいる
いつまでも夢のようなスピード
僕らが住む国を探している
その速さが視力
瞳の底から産まれる
高さ2mの山たち
かかとの中の気持ちが
地面を支えていて
僕らのさみしくない国が見える
そこにある歌が君の数を数えて
その大きさが視力
瞳の表面は乾いて
きれいに剥がれている
せめて砂に埋めたら
君と寂しさが生えてきた
内臓の船は食べられ
2mの山は踏み固められても
収穫の祈りをささげて
寂しさだけを刈り取ることが出来る
瞳の表面は乾いて
寂しくない国なんていらない
刈り残された君が
揺れながら風を産んで
僕の身体に刺さっている
その強さが視力
ここに書き写させていただきながら、はっきりとイメージが体感されてきた。
刈り取られる寂しさという丈の高い草や、その後にのこったのは、刈り取るときに
踏み固めてしまった君の気持ちと、そこここで細い茎の君といういろいろな草たち
が揺れながら風を産んでいる情景。そして草たちは鋭く僕の身体に刺さっている。
寂しさを粗末にした僕へ「寂しくない国なんていらない」と刺さるつよさが視力だ
というのだから、なんて激しい向き合い方をしているのだろう。書いた言葉がねじれ
ながら、濃く香る。言葉が熱を持っている。その熱に魅せられる。
[金沢21世紀美術館]
3月19日
いまここに言葉を置いて一日を終えようとするとき、夕方から昼それから朝へと
記憶を遡ったりしない。一日をすばやく飛び移って朝起きてからのことを思い出し
はじめるのはどうしてだろう。近い時間から遠い時間へと波のように伝ってゆくの
は苦手なようにできているのかも知れない。
りっとさん、とは樋口えみこさんを通して知り合ったのだが、りっとさんが第一詩集
『空にからだの船、青く』を草原詩社から里都潤弥の名前で出版した。樋口さんプロデ
ュースの、もういちど生まれるためにシリーズ、一号。おめでとうございます、りっと
さん、樋口さん。
この詩集のなかでとても凄い詩に私は巡りあった。タイトルは「視力」。こんなに難
しいものが詩にできるのだろうか、とふと多和田葉子さんの小説「旅をする裸の眼」の
言葉(視力とは裂け目なのでまさにそこが見えない)を思いだした。りっとさんは、その
見えないところを感じながら、見るという視力の意味からジャンプして自分の世界を詩
で開いてゆく。いい感じだなぁと思う。
視力 里都潤弥
瞳の中に海が産まれる
内蔵の船が泳いでいる
いつまでも夢のようなスピード
僕らが住む国を探している
その速さが視力
瞳の底から産まれる
高さ2mの山たち
かかとの中の気持ちが
地面を支えていて
僕らのさみしくない国が見える
そこにある歌が君の数を数えて
その大きさが視力
瞳の表面は乾いて
きれいに剥がれている
せめて砂に埋めたら
君と寂しさが生えてきた
内臓の船は食べられ
2mの山は踏み固められても
収穫の祈りをささげて
寂しさだけを刈り取ることが出来る
瞳の表面は乾いて
寂しくない国なんていらない
刈り残された君が
揺れながら風を産んで
僕の身体に刺さっている
その強さが視力
ここに書き写させていただきながら、はっきりとイメージが体感されてきた。
刈り取られる寂しさという丈の高い草や、その後にのこったのは、刈り取るときに
踏み固めてしまった君の気持ちと、そこここで細い茎の君といういろいろな草たち
が揺れながら風を産んでいる情景。そして草たちは鋭く僕の身体に刺さっている。
寂しさを粗末にした僕へ「寂しくない国なんていらない」と刺さるつよさが視力だ
というのだから、なんて激しい向き合い方をしているのだろう。書いた言葉がねじれ
ながら、濃く香る。言葉が熱を持っている。その熱に魅せられる。
[金沢21世紀美術館]

 3月13日
「共鳴、ここ・から」を見にいってきた。
21世紀を共に生き延びるための意識、共存、集合知への移行を説く長谷川祐子さん
の造った「エゴフーガル」という言葉と共に、見て回る。
個の境界を維持しつつ、意識の磁場を共有する「積極的な遠心力をもって他者や世界
とつながっていく、新たな主体のあり方」。そんな共鳴や振動を感じる作品たちだった
けれど、もっとも伝わってきたのは細い無数ロープでさまざまな日常の物を組み入れた
巨大なシャンデリアのようなサラ・ジーの作品だった。吹き抜けの階段のガラスのエレ
ベーターのところにあった。大きなコラージュなのに静かにかすかに揺れている。よく
みると地階に置かれた扇風機が首を振って回っていて、扇風機に結んだ紐が扇風機が首
をふるのにつれて大きなオブジェ全体を揺らしているのだった。
不安定な揺らぎや結ばれ方は、脳のシナプスの網目状に枝や蔓や細いワイヤーなどで様々
なものを結びつけた「ブレイン・フォレスト」にも感じられた。高い天井の広い空間いっぱいに
様々な物を結びつけ吊られた枝をみていると全てのことを忘れて見入ってしまった。ごくちいさ
な黄色や白や紫の花、赤い実、柄のとれた傘、花と葉で造った鳥、ペットボトルを切った
リボン、小さな恐竜、流木のような発泡スチロールのかけら、しおれた木の実や、よく見る
と本物の鳥の巣や蝉の抜け殻なども結びつけられている。スピーカーやイカ吊り船のランプ
もある。銀杏の黄色い葉、紅葉の赤い葉、枯れた笹の葉なども結んであり、きれいで見飽
きない。それらをソファーに仰向けに寝て見上げることもできた。様々な生活シーンや様々
な風景が、見つめていると見えてきた。春も秋も夏も冬も。脳の記憶はいまここにある展示
のようにいまあるのだということが感じられてくる。断片が細い繋がりで。
人々の脳が、枝に花や日常の物が結ばれて縦横に細く網の目になっているように、
人と人との関係も記憶として網目に結ばれている、危うく、けれどいまここに記憶として
灯りながらあり、別々に記憶が響きあっておおきな記憶を繋いでいると意識させられた。
私の脳の森もそんなふうに振動してきた。
別の部屋ではビー玉だけを広い床に並べて造った世界地図の作品は、ビー玉の危うさが、
ちょっと誰かが指で押したりしたら、世界が崩れてしまうというイメージを震わせた。
一緒にSさんとSさんの子供の小学3年生のともちゃんと見て回ったのだけれど美術館がガラス
の壁で円状にすべて覆われていたので外がみえてとても気分が楽だった。ともちゃんもプール
の底に入ったり、真ん中に池のある卓球台で遊んだり楽しそうだったのでよかった。
[それでも笑顔で]
3月13日
「共鳴、ここ・から」を見にいってきた。
21世紀を共に生き延びるための意識、共存、集合知への移行を説く長谷川祐子さん
の造った「エゴフーガル」という言葉と共に、見て回る。
個の境界を維持しつつ、意識の磁場を共有する「積極的な遠心力をもって他者や世界
とつながっていく、新たな主体のあり方」。そんな共鳴や振動を感じる作品たちだった
けれど、もっとも伝わってきたのは細い無数ロープでさまざまな日常の物を組み入れた
巨大なシャンデリアのようなサラ・ジーの作品だった。吹き抜けの階段のガラスのエレ
ベーターのところにあった。大きなコラージュなのに静かにかすかに揺れている。よく
みると地階に置かれた扇風機が首を振って回っていて、扇風機に結んだ紐が扇風機が首
をふるのにつれて大きなオブジェ全体を揺らしているのだった。
不安定な揺らぎや結ばれ方は、脳のシナプスの網目状に枝や蔓や細いワイヤーなどで様々
なものを結びつけた「ブレイン・フォレスト」にも感じられた。高い天井の広い空間いっぱいに
様々な物を結びつけ吊られた枝をみていると全てのことを忘れて見入ってしまった。ごくちいさ
な黄色や白や紫の花、赤い実、柄のとれた傘、花と葉で造った鳥、ペットボトルを切った
リボン、小さな恐竜、流木のような発泡スチロールのかけら、しおれた木の実や、よく見る
と本物の鳥の巣や蝉の抜け殻なども結びつけられている。スピーカーやイカ吊り船のランプ
もある。銀杏の黄色い葉、紅葉の赤い葉、枯れた笹の葉なども結んであり、きれいで見飽
きない。それらをソファーに仰向けに寝て見上げることもできた。様々な生活シーンや様々
な風景が、見つめていると見えてきた。春も秋も夏も冬も。脳の記憶はいまここにある展示
のようにいまあるのだということが感じられてくる。断片が細い繋がりで。
人々の脳が、枝に花や日常の物が結ばれて縦横に細く網の目になっているように、
人と人との関係も記憶として網目に結ばれている、危うく、けれどいまここに記憶として
灯りながらあり、別々に記憶が響きあっておおきな記憶を繋いでいると意識させられた。
私の脳の森もそんなふうに振動してきた。
別の部屋ではビー玉だけを広い床に並べて造った世界地図の作品は、ビー玉の危うさが、
ちょっと誰かが指で押したりしたら、世界が崩れてしまうというイメージを震わせた。
一緒にSさんとSさんの子供の小学3年生のともちゃんと見て回ったのだけれど美術館がガラス
の壁で円状にすべて覆われていたので外がみえてとても気分が楽だった。ともちゃんもプール
の底に入ったり、真ん中に池のある卓球台で遊んだり楽しそうだったのでよかった。
[それでも笑顔で]
 3月9日
心配なこと、あまり良くない方へ気がかりなとき、はてしなくネットサーフィンを
している自分に気付く。次ぎから次ぎへと興味を追ってゆきながら、やめられなくなって
しまう。心配事を忘れられるからという理由など頭にない。ただただ取り憑かれたように
やめられなくなって、目がきしんで、痛くなりだし、疲れて胸がつかえてくると、ようやく
吐きそうなほど気持ち悪くなって止める。言葉にしてみると、なんだか過食症や買い物が
止まらない症候群の感じと似ていると思った。ただ物ではなく情報を読む、ということ
に置き換わっただけ。心配から逃げているという意識ではなく、次ぎから次ぎへ細部
が枝分かれして、見たい読みたいものがどんどん移って移動してゆく。だから追いかける。
止められなくなる。酔ったようになっているのかも知れない。酔っているのだとしたら
飲酒に近いのだろうか。そんな日は睡眠時間もなくなるので次ぎの日は体が辛くなる。頭が
まわらないから考え込めない。それでカタルシスになっているかといえばそうでもない。
奇妙な混乱に落ちて不信感や落胆や苦しさが体を覆っているとき、ふと多和田葉子の
『ヒナギクのお茶の場合』を読んだ。すると混乱したところへ真っ直ぐに言葉のエネルギー
が注がれて、絡まったものがするすると解け脳がすっきりした。やっぱり多和田葉子の
言葉はいい。
川上亜紀さんの詩集『酸素スル、春』七月堂刊を読む。私の詩誌『エメット』に書いてくれた
「凹む夏」も入っている。螺旋階段がループしているようにうまく運ばない現実から、夢の
現実へ上っていってはまた降りてくる世界は独特な世界だ。夜眠れないのでベッドをずらして
スプーンで土を削りとってゆき、そのベッドの下が土だというのも変だが、私だけの墓穴が欲し
かったので掘るという理由も可笑しい。そして「その穴は「新明解」という名前になった」
という。この奇妙さは書くことで困難を超えてゆくときに起こるユーモア。川上さんの詩の言葉
は夢をくぐりながら手に負えない生を言葉を書く手とともに本人が一緒に伴走してゆくときに獲得
したユーモアなのだった。読みながら漬かりもせず溺れもせず私も共に伴走しながら、顔をゆがめた
りくすっと笑っていたりした。
[マスクをしたまま深呼吸]
3月9日
心配なこと、あまり良くない方へ気がかりなとき、はてしなくネットサーフィンを
している自分に気付く。次ぎから次ぎへと興味を追ってゆきながら、やめられなくなって
しまう。心配事を忘れられるからという理由など頭にない。ただただ取り憑かれたように
やめられなくなって、目がきしんで、痛くなりだし、疲れて胸がつかえてくると、ようやく
吐きそうなほど気持ち悪くなって止める。言葉にしてみると、なんだか過食症や買い物が
止まらない症候群の感じと似ていると思った。ただ物ではなく情報を読む、ということ
に置き換わっただけ。心配から逃げているという意識ではなく、次ぎから次ぎへ細部
が枝分かれして、見たい読みたいものがどんどん移って移動してゆく。だから追いかける。
止められなくなる。酔ったようになっているのかも知れない。酔っているのだとしたら
飲酒に近いのだろうか。そんな日は睡眠時間もなくなるので次ぎの日は体が辛くなる。頭が
まわらないから考え込めない。それでカタルシスになっているかといえばそうでもない。
奇妙な混乱に落ちて不信感や落胆や苦しさが体を覆っているとき、ふと多和田葉子の
『ヒナギクのお茶の場合』を読んだ。すると混乱したところへ真っ直ぐに言葉のエネルギー
が注がれて、絡まったものがするすると解け脳がすっきりした。やっぱり多和田葉子の
言葉はいい。
川上亜紀さんの詩集『酸素スル、春』七月堂刊を読む。私の詩誌『エメット』に書いてくれた
「凹む夏」も入っている。螺旋階段がループしているようにうまく運ばない現実から、夢の
現実へ上っていってはまた降りてくる世界は独特な世界だ。夜眠れないのでベッドをずらして
スプーンで土を削りとってゆき、そのベッドの下が土だというのも変だが、私だけの墓穴が欲し
かったので掘るという理由も可笑しい。そして「その穴は「新明解」という名前になった」
という。この奇妙さは書くことで困難を超えてゆくときに起こるユーモア。川上さんの詩の言葉
は夢をくぐりながら手に負えない生を言葉を書く手とともに本人が一緒に伴走してゆくときに獲得
したユーモアなのだった。読みながら漬かりもせず溺れもせず私も共に伴走しながら、顔をゆがめた
りくすっと笑っていたりした。
[マスクをしたまま深呼吸]

 3月7日
土曜日に佐藤淳一さんの写真展『瞼と森』にいってきた。毎年同じギャラリー
なので今年の写真に重なって去年の写真が見えた。そのむこうに一昨年の「air」の
時の写真も見えた。同じギャラリーで続けるのはこんなふうになるのかと驚いた。
もちろん覚えているものだけしか見えないけれど。今年は植物、動物、魚など生きて
いるものが目についた。そしていつも思うけれど立体感を現す線がいきていた。佐藤
さんは脊髄のバランス感覚とおっしゃっていたけれど、人のカメラを捧げる腕も、
向日葵の茂りうねっている茎も構造物のように立体的に感じる。そして水と草の緑と
花の黄色が生き物感を伝えてきた。
永代橋から墨田川を撮る。ギャラリーの直ぐ下が墨田川なので写真展と川は私の中
でセットになってしまた。花粉避けマスクをしながら、るんるん歩いた。
[瞬間のピンク]
3月7日
土曜日に佐藤淳一さんの写真展『瞼と森』にいってきた。毎年同じギャラリー
なので今年の写真に重なって去年の写真が見えた。そのむこうに一昨年の「air」の
時の写真も見えた。同じギャラリーで続けるのはこんなふうになるのかと驚いた。
もちろん覚えているものだけしか見えないけれど。今年は植物、動物、魚など生きて
いるものが目についた。そしていつも思うけれど立体感を現す線がいきていた。佐藤
さんは脊髄のバランス感覚とおっしゃっていたけれど、人のカメラを捧げる腕も、
向日葵の茂りうねっている茎も構造物のように立体的に感じる。そして水と草の緑と
花の黄色が生き物感を伝えてきた。
永代橋から墨田川を撮る。ギャラリーの直ぐ下が墨田川なので写真展と川は私の中
でセットになってしまた。花粉避けマスクをしながら、るんるん歩いた。
[瞬間のピンク]
 3月2日
元木みゆきの写真展学籍番号011145が銀座のガーディアン・ガーデンでひらかれている。
すごくよい。あの中にたっていると活性化される。
そして
元木みゆきの web版 学籍番号011145もはじまっている。
切り立った信頼関係。そう言いたくなる写真はどんなときにも神経を張りつめて、撮り
ながら人のなかに立っていた彼女のぎりぎりまで気をはりつめた鋭さ、真摯さ、に支え
られている。それだからこそ突き抜けた今をからっと見せてくれる。見たことのない写真
群のこの明るさはホンモノもニセモノもない。こんなふうになまなましく、解け合えず、
信頼しあい、あからさまに、隣り合って生きている身体を目撃したことが、いえ意識化
したことがあっただろうか。自分自身に問わずにはいられない。髪と首。空のなかの×。
赤いジャージの躍動。便器のそばの動き。笑う唇と歯。作業する体。教室の乾いた群れ。
直感と努力を総動員しなくてはこれらはなかった。荒々しく、しなやかに、なにものにも
とらわれていない。共感も苦しさも悲鳴も青空にばらまくようにして、周りの友達といっしょに
打ち上げ花火にしてしまった。生命感の花火大会。リアルタイムに見なくちゃ損。こんな
にがんばって見せてくれているのだから。
3月2日
元木みゆきの写真展学籍番号011145が銀座のガーディアン・ガーデンでひらかれている。
すごくよい。あの中にたっていると活性化される。
そして
元木みゆきの web版 学籍番号011145もはじまっている。
切り立った信頼関係。そう言いたくなる写真はどんなときにも神経を張りつめて、撮り
ながら人のなかに立っていた彼女のぎりぎりまで気をはりつめた鋭さ、真摯さ、に支え
られている。それだからこそ突き抜けた今をからっと見せてくれる。見たことのない写真
群のこの明るさはホンモノもニセモノもない。こんなふうになまなましく、解け合えず、
信頼しあい、あからさまに、隣り合って生きている身体を目撃したことが、いえ意識化
したことがあっただろうか。自分自身に問わずにはいられない。髪と首。空のなかの×。
赤いジャージの躍動。便器のそばの動き。笑う唇と歯。作業する体。教室の乾いた群れ。
直感と努力を総動員しなくてはこれらはなかった。荒々しく、しなやかに、なにものにも
とらわれていない。共感も苦しさも悲鳴も青空にばらまくようにして、周りの友達といっしょに
打ち上げ花火にしてしまった。生命感の花火大会。リアルタイムに見なくちゃ損。こんな
にがんばって見せてくれているのだから。